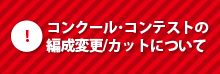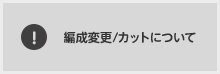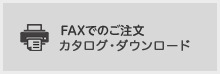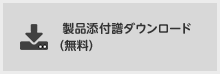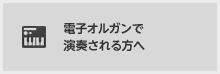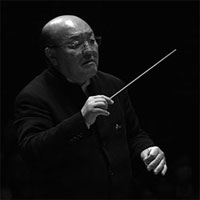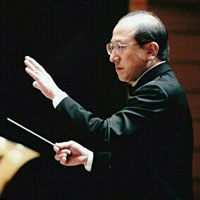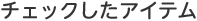教えて木内先生!【小編成 選曲編④】
2025年新作はこんな作品たち!
今年リリースの小~中編成の注目作12タイトルについて、バンド指導のスペシャリスト、木内恒先生に選曲アドバイスを頂きました!
長年指導現場で培われた視点からの作品解説に加え、演奏の際にポイントになってくる点も教えていただきました!
気になるあの曲を、名指導者の視点から一歩踏み込んで見てみましょう!
オスカー・ファンタジア/樽屋雅徳
Q.どんな曲ですか?教えて木内先生!
⇒バンドオリジナルのストーリーで作り上げるミュージカル音楽!
木内恒先生の解説
この曲は最初から最後までとにかく楽しく、まるで人気のミュージカルを見ているかのようです。こんな曲を自由曲に選んだバンドは楽しい夏を過ごせると思います。また演奏可能な最少人数は21人ですが、それ以下でも十分にこの曲の良さを味わうことができると思います。この場面のストーリーは?個々の場面はどんな踊りが?など想像しながら音楽づくりをしていける魅力がこの曲にはあります。ぜひメンバーの力を結集してこの曲の良さを楽しんでほしいです。
演奏のポイントは、ハーモニーを意識することと拍子の変化を演奏メンバーにしっかりと理解してもらうことだと思います。場面ごとに一つ一つ確認することで演奏した時にハーモニーが感じられると思います。また拍子は譜読み段階から拍をカウントすることが大切だと思います。低音パートはもちろん、ほとんどのセクションで音を重ねて書かれているので、初心者や経験の浅いメンバーがいても安心です。Vib.のソロは魅力的に演奏してほしいです。そのソロの前後に休みが作られているので、一番上手なメンバーが演奏することも可能だと思います。
Gr:3/Time:8:00
ホリーホック 復興の花/福島弘和
Q.どんな曲ですか?教えて木内先生!
⇒木管楽器の指使いや金管楽器の跳躍といった技術的な部分が最大限配慮された作品。
木内恒先生の解説
最少人数は17人で演奏可能になっているだけでなく、演奏しやすいよう随所に配慮されているので少人数でも福島さんらしいドラマティックで音楽の充実感を味わえる曲になっています。Trp.の最高音はGです。ソロはTrp.に2回Fl.に1回ありますが、それほど難しさは感じないと思います。歌心も満載で吹奏楽の醍醐味を十分に味わえる曲だと思います。
演奏のポイントは拍子の違いをメンバーでしっかり理解することだと思います。前半は4拍子が続くので安心して演奏できますが、後半は3拍子と2拍子が交互に連続して出てくる他、7/8拍子が現れます。4拍子は英語で3拍子は日本語、2拍子は“1ト2ト”、7/8拍子は“タトゥタトゥタトゥトゥ”でカウントさせると的確に演奏できるようになると思います。時々3/4に6/8が入ってくるので気を付けましょう。また打楽器は2パートで書かれていて2人でも演奏可能ですが、3~4人いれば一人ずつの負担が減るのではないでしょうか。
Gr:3/Time:6:30
女化稲荷月朧夜 ~狐の恩返し伝説による幻想曲~/阿部勇一
Q.どんな曲ですか?教えて木内先生!
⇒人数が少なくても、深みのある充実した音楽を表現できる作品。
木内恒先生の解説
バンドの人数が少ないと音楽的な深みが少なくなる場合がありますが、この曲はそんな心配はありません。音楽表現もスケールの大きさも大編成の楽曲と遜色ない曲です。メロディの美しさとリズムの躍動感がこの曲の大きな魅力になっています。Fl.とCl.のデュエットとFl.とA.Sax.にソロがありますが、丁寧に練習すれば心配ありませんし、金管の音域も無理がないように配慮されています。密度の濃い音楽を味わうことにできる曲ですので、意欲的なバンドにはぜひ挑戦してほしいです。
演奏のポイントは、音符(休符)の長さとバランスづくりだと思います。付点音符なのか複付点なのか、休符が入っている・入っていないなどを明確に分けることが重要です。この曲は打楽器がとても充実していますが、管楽器の人数によっては打楽器ばかり聴こえてしまう場合があります。打楽器のみの部分と管楽器と一緒の部分とでうまくバランスを取る必要です。特に和太鼓を使う場合はパワーがあるので要注意です。また拍子が変わる瞬間をしっかりと捉えることも大切だと思います。
Gr:3.5/Time:6:15
カインとアベル/広瀬勇人
Q.どんな曲ですか?教えて木内先生!
⇒1作品に込められたストーリーの展開(拍子の変化)を通して音楽的な学びを追求してほしい作品。
木内恒先生の解説
いつも魅力的な作品を書かれる広瀬さんですが、今回も期待を裏切らない作品となっています。編成は11人で演奏できるように書かれていますが、もっとメンバーが多いバンドにもぜひ取り組んで欲しいです。ソロはFl.に3回、Cl. / A.Sax. / Trp. / Trb.に各1回ずつあります。トゥッティで演奏する時よりも音楽的で魅力的なソロにしてほしいです。Pf.がオプションパートですが、もしPf.の堪能なメンバーがいる場合は、経験の浅いメンバーやハーモニーの薄さをカバーする助けになるかもしれません。
演奏のポイントは拍子の変化に対応することだと思います。作曲家が拍子を変えるのはそこに確かな変化が現れてほしいからだそうです。となると演奏者は拍子が変わる瞬間を確実に意識すべきだと思います。なぜ広瀬さんはそこにその拍子を書いたのか、作曲者のメッセージをしっかりと受け取りましょう。またこの曲は強いストーリー性を感じます。メンバーで登場人物や場面などを想像してみたり、メロディに歌詞をつけてみたりしてこの曲の良さを追究してほしいです。
Gr:3.5/Time:6:20
廻る天輪 ~英雄ロスタムと悲劇のソフラーブ/片岡寛晶
Q.どんな曲ですか?教えて木内先生!
⇒多彩な場面変化をバンド毎の個性で表現したい作品。打楽器が特に大活躍!(打楽器は2名から演奏可能)
木内恒先生の解説
とても内容の濃い音楽ですので意欲的なメンバーがいるバンドにはぜひ挑戦してほしい作品です。片岡さんの作品らしく打楽器セクションは大活躍で、セクションソロもあります。打楽器は4人ほしいところですが、2人しかいない場合のための楽譜も書かれていますので参考にしてみましょう。18人が最小演奏可能人数となっていますが、フルートとピッコロの持ち替えと打楽器2人にすると15人でも演奏可能です。またソロも多いのですが様々な楽器で演奏できるようにオプションソロの楽譜書かれています。B.Sax.が随所で重要な役割を果たしています。
演奏のポイントは何度も場面が変わるのでそのテンポや曲想の変化をしっかりとつけることだと思います。譜読みの段階で正確なリズムを確認しながら練習していくことが大切です。また後半の美しい旋律をどのように歌い上げるのかがこの曲の仕上がりを左右することになると思います。メロディに歌詞を付けて歌ってみたり、場面のストーリーをメンバーで作ってみたりすることで音楽表現がより明確になっていくと思います。
Gr:3.5/Time:8:10
希望のすべてに/八木澤教司
Q.どんな曲ですか?教えて木内先生!
⇒音楽経験の少ない演奏者でも取り組みやすい作品。是非メロディを歌って音楽の美しさを感じてほしい!
木内恒先生の解説
明るく美しいサウンドで魅力たっぷりな作品でありながら、とても取り組みやすい曲でもあります。その理由として最初から最後まで拍子が4/4であり、調も変ロ長調で中間部でト短調へ移行する以外は転調もありません。音楽経験の少ないメンバーにとってはとてもありがたいことだと思います。テンポの変化と楽器の組み合わせの変化だけで、こんなにもさわやかで魅力的な音楽になるのは驚きです。演奏可能な最少人数は14人です。特に難しいパートもありません。打楽器は3人でも演奏可能ですが、オプションパートも重要なのでできれば4人いてほしいです。最初の方にFl.とCl.の短いソロもありますが特に難しいものではありません。
演奏のポイントはその場面ごとの曲想の変化を明確にすることとリズムを正確に感ずることだと思います。ハーモニーもメロディもとても親しみやすく、音楽の美しさを感じられます。自分のパートを歌ってみるととても良い練習になると思います。またフレーズの途中に休符が入る箇所が何度か出てきますが、休符の前の音が短くならないように気をつけましょう。
Gr:2.5/Time:5:50
蒼翠幻想 ~千の想いとともに~/江原大介
Q.どんな曲ですか?教えて木内先生!
⇒和楽器をはじめとした打楽器が活躍!とってもエネルギッシュな和風の音楽が魅力的。
木内恒先生の解説
演奏可能な最小人数は15人ですが打楽器は4人(できれば5人)必要です。全編を通して打楽器が大活躍します。打楽器パートに元気でやる気に満ちているメンバーがいるバンドにはうってつけです。ソロはFl. / Cl. / A.Sax. / T.Sax. / Trp. / Trb.とたくさんありますが、どれも短めですのでメンバーへの負担は少ないと思います。(Fl.とA.Sax.には豊かな表現力が必要です)また、曲名からして分かるように和を感じさせる曲調で曲全体にエネルギーを感じます。
演奏のポイントはユニゾンや同じ動きをするセクションが多いことから、その動きやリズムそして音程を合わせることが必要になります。さらに強弱記号をしっかりと確認して演奏することが重要です。江原さんは細かなクレッシェンドやデクレッシェンド、「fp」を記入してくれているだけでなく「mp」や「mf」を丁寧に書いてくれています。この指示は作曲者からのメッセージですので大切にしてほしいです。それから管楽器の人数にもよりますが打楽器とのバランスには注意してください。本番前には広い場所でバランスの確認をしてほしいです。特に和太鼓はパワーがあるので気を付けましょう。
Gr:3.5/Time:7:30
吹奏楽のためのバラード第2番「春雷の凰」/田村修平
Q.どんな曲ですか?教えて木内先生!
⇒音域・リズム・フレーズ・拍子など随所に配慮がありつつも、音楽的な充実を兼ね揃えた作品。
木内恒先生の解説
各楽器の音域やリズム・跳躍の少ないメロディ・変化の少ない拍子など、経験の浅いメンバーにできるだけ苦労させず、しかし音楽的な充実感をできるだけ感じてもらいたいという田村さんの思いを強く感じる作品です。演奏可能な最少人数は16人です。打楽器は3人で演奏可能ですが、4~5人いれば表現の幅が広がると思います。Timp.とS.D.を中心に打楽器がバンドを引っ張る役割を担っています。ソロはTimp.の一カ所のみです。各パートが同じ動きをしていることが多いのも、経験の浅いメンバーにとってはありがたい配慮だと思います。しかし様々な工夫の中で音楽は躍動感にあふれ、随所に心を打つメロディが展開されています。
演奏のポイントは、打楽器パートのアンサンブルをしっかりすることが必要になってきます。また冒頭に実音「A」のユニゾンが重なっていきますが、ここはぜひしっかりと合わせたいです。また美しいメロディの動きはハーモニーの上に成り立っていることを感じながら演奏してほしいです。練習する時にテンポを落としてハーモニーを確認しながら進めていくとメンバーも理解しやすいと思います。
Gr:3/Time:6:30
オフィーリアの悲しみ/松下倫士
Q.どんな曲ですか?教えて木内先生!
⇒テンポ・拍子の揺らぎや絡み合うソロが音楽を深く彩る魅力的な作品です。
木内恒先生の解説
オプション楽器を入れない人数は22人となっています。打楽器は5パートでオプションはありません。昨今の吹奏楽事情を考えると中編成の楽曲と考えても良いかもしれません。またソロも多くFl. / Cl. / A.Sax. / Euph.そしてOb.です。Ob.はオプションとなっていますが、メンバーがいればぜひソロを聴きたいところです。スコアには代替え楽器の楽譜も書かれています。そしてオプションのパートも大切な音を受け持っているところもありますので、スコアをよくチェックしてほしいです。またEuph.にも大切なソロがあります。意欲的なEuph.奏者がいたらぜひトライしてもらいたいです。曲の内容はとても深く変化に富んだもので、やり応えがあり演奏効果の高い曲だと思います。
演奏のポイントは、テンポと拍子の移り変わりを正確に演奏することだと思います。何度もテンポが変わりますしrit.やstring.があります。最初のうちはインテンポで練習し、楽譜に慣れてきたらテンポを変えていくと正確に演奏できるようになります。また拍子も次々と変化していきます。楽器で演奏する前に拍子をカウントしてから楽器で演奏すると、より正確に演奏できるようになります。この曲は様々な場面がめまぐるしく展開しますので、ストーリーをメンバーで話し合ってみるとこの曲の魅力に近づいていくと思います。
Gr:4/Time:7:30
ボイジャー・プログラム -太陽系を超えて-/下田和輝
Q.どんな曲ですか?教えて木内先生!
⇒爽快なリズムと疾走感のあるメロディや歌心もつ場面など、壮大なスケールを持つ音楽は演奏者がわくわくすること間違いなし!
木内恒先生の解説
この曲は最初から最後まで吹奏楽の魅力満載です。爽快なリズムと疾走感のあるメロディそして歌心と、演奏者にとってわくわくする場面が次々に展開されます。演奏可能最少人数は9人ですが、もっと人数がいればより迫力が増すと思います。打楽器は5パートですが、代替えの楽譜も書いてくれているので、5人より少なくても演奏可能になっています。
演奏のポイントは拍子の変化に対応することだと思います。変拍子が効果的に使われていますので、カウントしながら練習して正確に演奏できるようにしてほしいです。また強弱はしっかりとつけなければなりません。「p」と「mp」、「mf」と「f」の違いをしっかりとつけていくべきです。また曲の前半と後半に長い音(トリルも含む)が使われています。この長い音を演奏する時は心の中でしっかりとカウントしましょう。そしてどんなハーモニーが使われているかをぜひ確認しながら練習に取り組んでほしいです。この曲はドラマティックな展開やラストへ向かうエネルギーを感じることでその良さが感じられると思います。宇宙空間で繰り広げられるストーリーを考えてみると曲のイメージが広がるのではないでしょうか。
Gr:3.5/Time:8:00
グラヴィテーショナル・ウェーブ/石川健人
Q.どんな曲ですか?教えて木内先生!
⇒場面のコントラストがハッキリした、エネルギッシュでダイナミックな作品!
木内恒先生の解説
この曲は冒頭と後半がとても激しい音楽ですが、中間部は一転して実に美しく優しい音楽となっていてこのコントラストがうまく表現できることが大切だと思います。技術的に難しいところが多いので意欲的なバンドに向いていると思います。しかし丁寧に1小節または1拍に注目して楽譜を読んでいけばそれほど複雑に書かれているわけではないので、経験の少ないメンバーでも演奏できると思います(丁寧な練習が必要になります)。打楽器が効果的に使われていて使用する楽器の数も多いので打楽器パートが充実しているバンドにこそぜひトライしてほしいです。打楽器は6パートです。
演奏のポイントは拍子がめまぐるしく変わるのでカウント練習が不可欠です。曲の後半には3/4の中に6/8を感じる場面もあるので、スコアをよく読んでほしいです。また細かい連符にしっかりと息を入れて吹くことも大事になります。中間部をより美しく演奏することが必要ですが、そのためにも最初はスラーをとって正しい音価と音程を確認しながら練習していくべきだと思います。それから休符前の音が短くならないように注意してほしいです。その理由は短い音は乱暴な演奏に聴こえる場合があるからです。難しい箇所が多い曲かもしれませんが、ぜひ挑戦してエネルギッシュでダイナミックな演奏を創り上げてほしいです。
Gr:3.5/Time:6:45
ラプソディア・アパッショナータ/野呂 望
Q.どんな曲ですか?教えて木内先生!
⇒旋律の美しさが魅力の作品!和声の移り変わりを意識して取り組んでみてください。
木内恒先生の解説
この曲の魅力はメロディの美しさです。次々と心に残るメロディが続くので演奏者にとっては嬉しい曲だと思います。演奏可能人数は19人で打楽器は3人で演奏可能です。しかしオプションパートにVib.やGlock.のソロがあるのでメンバーが足りない場合は交代で担当したり、S.D.の横にSus.Cym.を用意すればオプション楽器の代替も行い3人でも演奏可能だと思います。ソロはFl. / Cl. / A.Sax. / Vib.ですが特にA.Sax.はとても重要になります。打楽器のセクションソリもあります。
演奏のポイントはまずは転調です。何度か重要な転調が出てきます。経験の浅いメンバーに転調の意味や調号の違いをしっかり理解してもらい、作品に取り組んだ方が良いと思います。またメロディに歌詞をつけたり曲のイメージをふくらませたりすることで、よりクリアにそして表現力あふれる演奏になると思います。同時にハーモニーの進行を意識させることで音楽に説得力が出てくるので、合奏練習の中で曲のハーモニーの動きを確認しながら進めてほしいです。
Gr:3/Time:7:30
木内恒(きのうち・こう)

2007年木内音楽賞受賞。2011年度文部科学省優秀教員表彰受賞。ノースアジア大学明桜高等学校吹奏楽部副顧問。日本ホルン協会理事。あきた芸術劇場「ミルハス」音楽部門アドバイザー。
◇木内先生による演奏&練習のためのワンポイントアドバイス!
連符の多い楽譜を『黒い楽譜』と言ったりしますが、演奏者によっては苦手意識をもっている場合もあるでしょう。連符を正確に練習するためには1拍(または半拍)の中に音がいくつあるのか最初に確認してみると分かりやすくなると思います。経験の少ない演奏者であればあるほど連符をまとめて一気に演奏しようとしてしまいます。そうなるとなかなか正確には演奏しにくくなってしまいます。1拍や半拍(または3連符)に16分音符4個なのかあるいは5連符なのか丁寧に確認してから練習(時には言葉を当てはめるなど)するとしっかりと演奏できるようになると思います。
変拍子の練習は?
変拍子はその曲の魅力でもあります。しかし、なかなかきっちりと演奏できない時があります。演奏者が拍子を曖昧にとらえていたりするからだと思います。合奏で変拍子を確認するには
①メンバーがしっかりとカウントする(4拍子は英語で、3拍子は日本語で、7/8などはカタカナなど)
②指導者がカウントしてメンバーは吹きまね(打楽器は叩きまねや練習台などを叩く)
③楽譜通りに演奏する
の手順で進めるとだいぶ正確に演奏できるようになると思います。 !