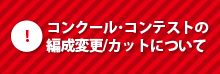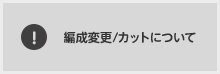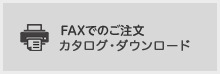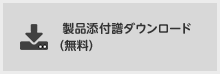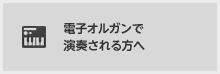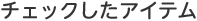- あ行
- か行
- さ行
- た行
- な行
- は行
- ま行
- や行
- ら行
- わ行
鎌田拓也
部門:中学校(30人)
本番までの練習時間:7ヶ月
俗にいう「ポップス奏法」もこの曲を攻略する上で大事になります。特に中学では、使い分けができていないバンドが多いと思うので、プロのスタジオミュージシャンの演奏を参考にしてください。配置についてもドラムセットを真ん中に置く、ソロはスタンドプレイで行うなど思い切った仕掛けも重要です。練習期間7ヶ月としましたが、管楽合奏の全国大会までの練習期間を表しています。
ユンナ
部門:(8人)
本番までの練習時間:1ヶ月~2ヶ月半(2回挑戦)
1回目:Trp.3人、Hrn.1人、Trb.2人、Euph.1人、Tuba1人
2回目:Trp.3人、Hrn.1人、Trb.3人、Tuba1人
で、演奏しました。私が、2年生のときは、リーダーを務め、全国までのぼりつめることができました!! いつも、基礎練をしていれば、だいたいできます。しかし、最後の方は音量と音質が大事になってきます。Trb.とTrp.でタンギングが揃わなかったり、裏のハーモニーがハモりませんでした。タンギングは、練習時、足踏みをして改善しました。ハーモニーは、全員がピッチを揃える時間を3時間の練習の中で1時間とりました。『サウンドトレーニング』という、基礎用の楽譜でピッチだけでなく、音のスピードなども、意識しました。
KAWASUI
部門:高等学校(3人)
本番までの練習時間:2ヶ月
音域がメロディーと伴奏が逆転するところがありましたので、音域を変えたり役割を変えて対応しました。(作曲者の片岡先生にお願いした部分が大きいです)
新型コロナの影響で、パート練習が中心になるのでアンサンブルの練習はちょうど良かったと思います。録音をマメに行い、課題を見つけてまた練習するような毎日でした。この練習も長続きはしないので、Fl,Fl,Clの三重奏でも同じ曲を練習し、互いに聴きあって課題を指摘したりしました。
さらに、6人一緒に演奏することで互いのアンサンブルの良いところを吸収し、新鮮さを感じながら練習しました。フレキシブル三重奏の楽譜ですが、6人、さらにそれ以上の人数でも十分演奏できる作品だと思います。
ゆっかーラブ
部門:中学校(21名)
本番までの練習時間:3ヶ月
R.F
部門:高等学校(25人)
本番までの練習時間:4ヶ月
Gからはpになっていますが、しっかりと響きのある音で練習してから強弱の設定をした方が良いと思います。またフレーズの頂点を明確に決めて練習に取り組むと良いと思います。
練習番号Iからのフレーズも、練習番号Aと同様に練習できると思います。
83小節目からのtuttiのフレーズですが、3回出てきます。3回目にはペザンテが書いてありますので、そこをどう演奏するかの計画が大切だと思います。練習方法として同音(例えばFの音)などで一度音形を整えてから練習すると良いと思います。 練習番号Mからのトロンボーン主体としたメロディーですが、装飾音にアクセントがついています。息の使い方を楽器を持たずに練習してから、曲の練習を始めると良いと感じます。また他の鈴木英史作品(チンギスハーンなど)にも同様のアクセントが見られますので、参考演奏などを聴いて雰囲気を掴むのも良いかもしれません。
練習番号Nからの木管のフレーズは8分音符の4つ目(E♭)が沈みやすいので(音量も音色も)特に注意する必要があると思います。このあたりも前述の練習方法が有効だと思います。
全体的にパート練習やセクション練習で音形を揃えたり、吹き方を揃えたりする箇所がかなり多いので生徒だけでも練習しやすい作品だと思います。またトランペットにハイトーンが多用されていますが、ソプラノサックス やクラリネットで被せて書いてある箇所も多いので、金管楽器の高音域に不安があっても取り組みやすい作品だと思います。
T.M
部門:中学校(50人)
本番までの練習時間:3ヶ月
テクニックを見せるというよりは合奏力での勝負です。
ホッコリ
部門:高等学校(3人)
本番までの練習時間:半年
演奏できたときの達成感はとてもよいと思います。
さい
部門:中学校(40人)
本番までの練習時間:6ヶ月
Y.T
部門:中学校(40人)
本番までの練習時間:5ヶ月
ボンボン
部門:高等学校(25人)
本番までの練習時間:3ヶ月
冒頭のブレスの音や掛け声に意外と苦労するが、これが大事なので我慢 汗
マーチの部分では始めのピッコロに処理を合わせるように注意しました。一緒に吹いたりしてた。
最後の部分は思いっきり歌い上げる事が重要です!
大体合奏では一番始めとマーチのリズム練、ラストのコードの練習を重視してた。
本当に良い曲なので、絶対に良い思い出になる!
鎌田拓也
部門:中学校(26人)
本番までの練習時間:3ヶ月
鬼の持つ恐ろしさと、人間の愛の2面性を表現するには、管楽器でいえば息のコントロール、打楽器でいえばストロークのコントロールがポイントとなります。特にスピード感ある音を出せるようになると、きれいな部分や弱奏の部分でも応用ができると思います。コロナ禍で通常通りの練習ができない中でも独自大会のコンクール曲として取り組みました。合奏時間は短かったものの、セクションやパートごとしっかりと組み立てていけば曲がしっかりと仕上がります。アンサンブルの精度をあげたり責任感を持って演奏することに気づけた1曲でした。中学生の小編成バンドでも取り組める曲です。
M.S
部門:その他(132人)
本番までの練習時間:3週間
短期集中の練習だったので、合同練習の初日に作曲の背景(震災当日の閖上の様子、避難所の様子など)を説明し、イメージを共有しました。全員、震災を経験していたので、イメージの共有は早かったです。当然、悲しく辛い想い出をした生徒もいるはずだったので、曲のエンディングで希望を抱いて未来へ繋げる若者のエネルギーを表現することで総文祭のフィナーレを飾ろう!!と全員で前向きに取り組むようにしました。
「衝撃」を象徴するイントロは、想定外の事態を音楽で表現するために、大音量や鮮明なリズムを発音できるような練習を繰り返しました。
イントロ後の「静寂と不安」を象徴する場面では、遅いテンポの中で動く旋律のウネリをあわせることが難しく、生徒同士のアイコンタクトや身体の動きにあわせてタイミングをあわせるようにしました。 「怒りと悲しみが混ざり合う混乱、焦燥」を表す速い部分は、100名を越える大バンドであったために縦の線をあわせるのにとても苦労しました。短期間の練習だったので、最初の段階で打楽器のリズムセクションの練習を重点的に行い、合奏では打楽器に全体を引っ張ってもらう形をとりました。コンクールの場合はメトロノームを利用して全員で遅いテンポから少しずつ速くしていく練習方法の方がよいかと思います。
「朝陽のコラール」の場面では、管楽器奏者に指定された音のクロテイル、グロッケンの音板(釣り糸で吊す)、トーンチャイムを個々に渡し、演奏してもらいました。合同演奏だったので、4つの学校で楽器の組み合わせを別々にし、それぞれの学校の中で1つの場面を表現する音楽にしてもらいました。その結果、4群の『キラキラ』が密集してくるような演奏効果になりました。
「祈祷」のチャイム連弾は2人のタイミングを合わせるのがとても難しいです。腕の振り方、呼吸の取り方などあらゆるタイミングをシンクロさせる練習が必要です。
「復興を想い描く」中間部では、木管群のユニゾンのバランスをどうとるか悩んだ結果、前半はクラリネット、盛り上がった後の後半はサックスを中心にサウンドを整えました。場面毎に木管群のバランスの配合を工夫すると色彩感の富んだ中間部になると思います。
「祭」の部分では、題材となった「閖上太鼓」は当時、復興のシンボルとして各地で演奏されていたので、復興のエネルギーを聴衆に伝えることを重要視しました。そのため安全運転ではなく、空中分解のリスクを恐れず演奏できるかできないかギリギリまでテンポを上げて演奏しました。荒い演奏だったかもしれませんが、総文祭での初演直後の鳴り止まない拍手を振り返ると、全国から集まってきた高校生の皆さんに「想い」の伝わる演奏であったのだと思います。
テーマがとても重いのですが、是非、作曲の背景にある東日本大震災について、今一度、見つめ直してから「想いの和々」に取り組むことをお勧めいたします。
yasuyasu
部門:高等学校(38人)
本番までの練習時間:4ヶ月
とにかく、片岡先生らしい躍動感のあるリズムと、うっとりするメロディ。歌いやすいし、曲の世界観に入りやすいし、楽譜そのものが自然と音色を作ってくれるような魅力があります。グレードは4なので、ある程度の力は必要ですが、全体的に無理のない音域で書かれていると思います。本番は事前に片岡先生の指導の甲斐あって満足する演奏ができました。少し補足するなら、指揮者のセンスも必要かも?!ゆったりの所はテンポ通りより緩急つけて揺らすくらいのスパイシーがあると更に効果的かもです。
さい
部門:中学校(50人)
本番までの練習時間:6ヶ月
よー
部門:その他(55名)
本番までの練習時間:5ヶ月
石ちゃん
部門:中学校(50名)
本番までの練習時間:4ヶ月
ひろ
部門:高等学校(23人)
本番までの練習時間:2ヶ月
#や♭が多く、速いパッセージが多いので、まずはゆっくりとしたテンポからコツコツと根気強く練習することが大事です。強奏部では力任せに演奏するのではなく、丁寧に演奏することが大切です。音量ではなく、小編成吹奏楽ならではの密度の高いアンサンブルを意識することで、バルトーク独特の土俗的な質感が出せると思います。
コントラバス、唯一の打楽器であるティンパニは特に高い技術と表現力が求められます。ティンパニはベリーハードの攻撃的なマレットではなく、音程感とリズム感が出るヘッドが小さめのマレットをご検討ください。
舞台上での楽器配置についてですが、ひな段が2~3段ある場合は、あえて1段目のみ使用することを強くおすすめします。舞台いっぱいに広がって演奏するとステレオ感は出ますが、拡散した響きになり、アンサンブルも乱れやすいです。コンパクトな舞台配置で、室内楽的に演奏できると良いと思います。ちなみに私のバンドでは、前列に下手からクラリネット・フルート、2列目下手からトランペット・ホルン・センターにティンパニ・ユーフォニアム・トロンボーン、ひな段にアルトサックス・テナーサックス・バスクラリネット・コントラバスを配置しました。
ティンパニをひな段に乗せないことで、コンクール本番でのセッティングもスムーズに行えましたし、センターに配置することでアンサンブルの要にもなりました。会場とバンドの相性の関係もあるので、色んな配置パターンを試してみるのも楽しいと思います。
Nerima Brass Players
部門:―
本番までの練習時間:4日
青空
部門:高等学校(1人)
本番までの練習時間:3ヶ月
ゆっくりのテンポから見落としの無いように練習して、拍子感を大事に演奏するのが良いと思う。
また、演奏にはスネアドラムとスティックだけでなくマレットやブラシが必要になる。演奏の都合上、パーカッションスタンドを2台設置して演奏することをお勧めする。
桶川哲也
部門:高等学校(33人)
本番までの練習時間:生徒たちは約8ヶ月、自分は約5ヶ月
前任の先生が曲を決めてくださり、礎をつくってくださっていたおかげで、自分よりも生徒たちの方が曲を理解している状態でのスタートだったことを覚えています。
先の吹きレポ(柴田和顕さん)にもあるように、中橋愛生先生の作品の中では、比較的取り組み易い作品だと思います。
主なソロパートに記載があるように、たくさんの楽器が活躍します。ソプラノサックスのソロは2回出てきて、他のソロよりも長いので特に重要かと思います。(当時ファゴットパートがいなかったので、バリトンサックスがファゴットパートのソロを担当しました)
練習する上で苦労したことは、トランペットの音域がイントロとエンディングで少し高く、せっかくの見せ場で外してしまうと目立ってしまうので、他のパートよりも多く練習に付き合った記憶があります。他にも木管楽器は細かい音符の動きが多いですが、部活以外の時間も使って自主的に練習して乗り越えてくれました。
ステージセッティングですが、私のこだわりで、打楽器を主にステージ下手にセッティング、但しウッドブロックとボンゴをステージ上手にセッティングし、74小節目から交互に動きがあるテンプルブロックとウッドブロック、90小節目からのテンプルブロックとボンゴ、この場面で遠くから近づいてくるように聞こえる様子をイメージして、打楽器の効果が出るように工夫しました。他にも、ステージ中央にヴィブラフォン、その下手隣にハープ、上手隣にコントラバスをセッティングし、全体の調和と音量のバランスを意識しました。
私は運が良いことに、明浄学院高等学校吹奏楽部さんの素晴らしい初演をアクトシティ浜松で聴いていました。2012年のバンドクリニックで一番印象に残った演奏が彩雲の螺旋でした。その時の印象は華やかな冒頭、中間のソロ部分はそれぞれが役割をもって流れを作り、後半は旋律の美しさをどのように表現するか。大きく分けてこのような印象を受け、練習の際もそのイメージを常に持っていました。(個人的には90小節目からの旋律と、130小節目からの旋律が大好きです…!)
就任した初年度で、たくさんのドラマがありましたが、目標にしていた「日本管楽合奏コンテスト」(2016年)に出場させていただくことができ、いつも前向きで思いやりのある高校3年生8人を中心とした、努力を怠らない33人の生徒たちと素敵な作品に出会えたこと、文京シビックホールに「彩雲の螺旋」が響いたことは一生の思い出です。
柴田和顕
部門:中学校(50人※2支部2校で3回取り組みました)
本番までの練習時間:6ヶ月
この曲に限らず中橋先生の曲は声部が多いためパート練習は生徒に「この3和音を合わせ」など指示は与えやすい。伸ばしや♬や3連などのファンファーレなどが該当する。
Tuttiで基本4和音以上が多いため冒頭のファンファーレは
・3和音だけを組み7thを乗せる
・5度間で重ねる
などは工夫が必要。
13小節目からのSax4重奏は3和音で動くのでSaxが充実している学校は魅せれる(S.Saxはソロがあるため)
サックス、ファゴット(バリトンサックスでも可)ユーフォニアムなどにソリストがいる学校向け。金管が♬などタンギングが明確に発音できる技術は必要。
指導に行った中学で取り組み、2校で東海大会、北陸大会まで行けました。
部活動ガイドライン前の話なので練習時間が短すぎる中学には難し過ぎると思いますので、今なら高校生向けかなと思います。
yasuyasu
部門:高等学校(46人)
本番までの練習時間:4ヶ月
まず、出だしの一発目、難しいです。。。粒、音形、ハーモニーバランス、メンタル等なかなかうまくいかず苦労しました。 ハイテンポの所は比較的ノリ良く演奏できますが、中盤にある、ローテンポの箇所はいろいろなことが要求されるので、かなり時間をかけていかないと単調になります。後半はとにかく、ホルンとティンパニの力量が試されます。スタミナを維持し、怖じけず堂々と吹ける事が必須です。それがクリアできると他のパートも自然と乗ってくる事間違いなしです。
グレードも4程度なので幅広いバンドがチャレンジできるでしょう。昔から、自由曲として演奏されていた名曲を是非やってみるのはいかがでしょうか。
あざらし
部門:中学校(50人)
本番までの練習時間:3、4か月
また木管はソロもあるので、どの楽器もそれなりの実力がないとつらいと思う。
個人的に2楽章のE♭Clarinetのソロはかなりハイレベルだと思う。byベークラ吹きでも金管もかなりつらいはず…。
特に1楽章のHornのハイDは鳥肌ものだから当てたら超かっこいいと思う。
でもHornはそのあともゲシュトプあるし、ロウB♭(またはそのオクターブ下のB♭)も出さなくちゃいけないし、で相当つらいと思う。(特に1st)
この曲はできたら楽しいだろうし、かっこよくなると思うが、その分、かなりの努力をしないといけない。
アンドレ
部門:その他(7人)
本番までの練習時間:2ヶ月
アレグロは各楽器でリズムを噛み合わせるのが難しく、練習番号ごとに区切って反復練習した。特に(9/8+6/8)後のトロンボーン3本のみでの速いパッセージはとても難しい。
アンダンテ前のティンパニのソロは、その後の金管が入るタイミングが取りづらく、何度も練習した。 クライマックスのアンダンテの部分は強奏から弱奏に落とし、クレッシェンドをかけていくのが体力的に厳しかった。特にトランペットは最後のファンファーレまで吹き続けるだけで一苦労。 全体を通して、特にトランペットに持久力が求められる曲であり、技術面では、どのパートもある程度吹ける人でなければ厳しい。
しかし、曲の構成などとても美しく勉強になり、音響も素晴らしい曲なので、チャレンジする甲斐がある。
kenshin.btrb
部門:高等学校(5人)
本番までの練習時間:2ヶ月
TAKU
部門:中学校(28人)
本番までの練習時間:4ヶ月
同じフレーズがいろいろなパートに引き継がれながら繰り返されるため、リズムのニュアンスを揃えることが大切です。特にCなど、クレッシェンドの頂点でのキメのリズムは重点的に合わせると良いでしょう。また、Rなど速いテンポの中で歌う部分を魅せられるとより良いです。
トランペットは最高音がGと低めですが、少し高い音域で吹き続けるのでバテやすいです。本校では各パート2人ずつ割り当てられたので交互に演奏する部分を作れましたが、上級生が複数いないとスタミナ面で辛いかもしれません。
また、打楽器はティンパニとタム、コンガ&ボンゴ、スネア&ハイハットの皮物&金物のアンサンブルと、鍵盤のアンサンブル両方があるので、オールマイティに練習する必要があります。
19名から対応とはなっていますが、吹きっぱなしになるパートが多いこと、打楽器の持ち替えが辛い部分もあることから、トランペット、打楽器はもう1名ずつ多くいると安心です。クラリネットも各パート2名いるとより安心です。クラリネットの2ndはシャルモー音域の部分が多いので、1年生でも吹きやすい楽譜になっていました。
みつ
部門:中学校(26人)
本番までの練習時間:3カ月
クラメインの話にはなりますが…
Aの部分がクラリネットのソリなので、1stの先輩と繰り返し練習を重ねてリズム、ニュアンス、テンポが合うようにしました。
音源聴いたりスコア見た方はお分かりかもしれませんが、どのパートにも活躍するところがあると思います。
木管はとにかく指いっぱい動かします。テナーとバス、バリトンあたりは裏メロや伸ばしもありますが、動かすフレーズはきついと思います。それ以外の木管はとにかく忙しい。最後に連符がお迎えしてくれます(^з^)-☆
クラ2ndはサックスのソロ8小節と2小節分の休み以外ほぼ何か吹きっぱなしです。きついです。初めは。毎日基礎練と一緒に続けると絶対できるようになります。継続は力なりです。
金管は冒頭部分はしばらく出番が無いと思うので、体力温存するといいと思います。
パーカはスネアとハイハットが難しいらしい(パーカッションパートの同級生の話による)です。シロフォンも大変だと思います。
この曲は場面ごとに曲想が移り変わるように言葉にできない美しさがあるのでそれぞれのフレーズに感情をこめて私は吹いていました。先生にも吹く時の感情や気持ちを大切に、と言われました。
また、合奏の時には和音の部分をメインに、目を閉じて他のパートとのピッチや響きを確認しました。和音の部分というのは、例えば最後のCとGとEの部分。全員で自分のパートの音を奏でることで根音、第三音、第五音のバランスをみます。
本番前のリハ室でもしてたので、これは必ずするべきです!!!
練習を初めて最初はとても難しかったですが、クラリネットのソリだけでなく中盤のクラリネットとホルンが中心になったコールアンドレスポンスも楽しかったですし、サックスのソロや低音の裏メロも聞いていてとっても楽しかったです。
どのパートもそう簡単に吹けるもので無いと思います。
でもやりがいはすごく大きいし、私は福島弘和さんの曲大好きなので楽しかったです!!
これから吹く人、頑張ってください!!
応援してますo(^o^)o
拙い文章失礼しました。
R.F
部門:その他(32人)
本番までの練習時間:5ヶ月
つぎに練習番号G以降に現れるタンギングを含む連符ですが、ここは奏者のシングルタンギングとダブルタンギングの中間のようなテンポ指定なので(木管楽器の奏者は早いタンギングに慣れているかもしれないが、トランペットにはちょっと厳しい?)まず曲作りの段階でこの部分を想定して、テンポ設定をする必要があると感じます。練習方法としてはタンギング部を8分音符に一度置き換えて息のスピード感を練習したうえでタンギングに戻すとうまくいきました。
練習番号Mから練習番号Vあたりにかけてテンポが少しづつ上がっていくが、特にPの前辺りでテンポが上がり過ぎてしまう傾向があるので、注意が必要です。この辺りはメトロノーム使いながら計画的に練習を進めていったほうが良いと思います。
最後に全体を通して金管楽器はハイトーンと息の長いフレーズ(終結部はfffのロングトーンが続く)作品なので、強弱の設定も含めて全体でどこを聴かせるかを考えながら練習を進めていくと良いと思います。
T.M
部門:高等学校(37人)
本番までの練習時間:5ヶ月
パーカッション♪
部門:中学校(-人)
本番までの練習時間:-
yasuyasu
部門:高等学校(43人)
本番までの練習時間:4ヶ月
譜読みは特別ややこしいリズムもなく、比較的スムーズに行きました。
ポイントとしては木管は無理な音域はありませんが、とにかく指練習必要
フルート2本はそれなりの演奏力がないと後半の二重奏は厳しいです。
金管は、メロディはあまりありませんが、ファンファーレ的要素が多いため、確実に当てる練習やハーモニーをきちんと感じさせることが重要。また、金管は2ndまでしかないため、金管は少ない人数、又はスタミナの使い分けが可能なのが利点です。 打楽器は上記の通り鍵盤は使わなくても演奏可能な程編成がシンプル。ただ、いっぱい叩きたい生徒には物足りないかも?でも 少ない分効果音要素を大きいです。
総合的には選曲に、私も部員も後悔なく、取り組めた曲でした。機会があればもう一度挑戦したいですね。
アザラシ
部門:中学校(18人)
本番までの練習時間:3~4か月
(初心者の方にオススメ)
フレキシブルパートもあるので、少人数の団体や、オーボエやファゴットなどのダブルリード楽器が無くても演奏できます。
ちなみに私の学校では、コンクールDの部で演奏しました。
(Ⅱの詩をかなりカット)
メロディーラインを複数のパートが吹いているので、パートごとに人数が偏っていても、比較的やりやすいですし、バランスも悪くなりにくい曲だと思います。
ソロもありませんので、安心して吹くことができる曲です。
みぞれ
部門:-(48人)
本番までの練習時間:10ヶ月
れんこん
部門:中学校(28人)
本番までの練習時間:4ヶ月
石ちゃん
部門:中学校(30名)
本番までの練習時間:4ヶ月
ボンボン
部門:中学校(48人)
本番までの練習時間:6ヶ月
Aからは、DマイナーとD♭メジャーで音がぶつかる仕組みになっているので、別々に合わせたほうがいいと思います。ただし、その場合のFはマイナーとメジャーで和音の取り方が真反対ですから、平均律でも良いのかと思います。
それから、すぐDに飛びます。
ここからは、テンポも早く、音合わせに苦労しますし、短い音符ですので、汚くなりがちです。木管の連符も誤魔化さず、しっかり合わせてください。38~39小節間の四分音符は、どの楽器も短くしない方が、かっこいいと思います。40小節目の32分音符は全体で合わせようと思うとかなり厳しいです。私たちは最後までクリアにできませんでした。
E前はおそらく書いてなくても、自然とrit.したくなりますし、したほうが良いと思います。原曲のオペラでも、大抵、少しrit.しています。
このEまでで印象が決まると思います。これは決め切りたい所です。まだまだこの曲の壁は厚いですが、やっていくうちに非常に楽しくなります。
ぜひ、原曲のオペラも見てください。演奏がガラッと、変わるはずです。
yasuyasu
部門:その他(5人)
本番までの練習時間:4日
T.M
部門:高等学校(51人)
本番までの練習時間:4ヵ月
大阪府立和泉高等学校吹奏楽部
部門:高等学校(76人)
本番までの練習時間:3週間
なお、この演奏動画は、作曲者Rossano Galanteさんにも確認していただいております。
ご投稿いただいた動画はこちら
さい
部門:中学校(50人)
本番までの練習時間:4ヶ月
Nerima Brass Players
部門:その他(3人)
本番までの練習時間:3回程度
◆実際の演奏動画をご投稿いただきました!
https://youtu.be/kGh-6ClPTTM
さい
部門:中学校(50人)
本番までの練習時間:5ヶ月
こう
部門:その他(30人)
本番までの練習時間:2ヶ月
全体的に表現力がかなり必要になるかと思いますが、小編成~中編成でも取り組み甲斐がある作品でした。
楽器変わりすぎて泣きそう
部門:高等学校(6人)
本番までの練習時間:1ヶ月くらい?
T.T
部門:高等学校(55人)
本番までの練習時間:4ヶ月
冒頭のsoloと12/8の拍子でのセクションの動きが見せ場なので、Trp,Sax,Clなどを目立たせたい又は自信のあるバンドは選曲すると良いかと思われます。楽譜が良いのでとても良く鳴ってくれます。
その中でも全体を通して、強奏でのfが同じ色にならないで、しっかり整理するとより美しくなると思います。
特にPicc.Obのsolo後の四角1と最後クライマックスは、優先順位を決めて縦や音形を揃えると素敵になると思います。中間部はmpなどでも消極的にならず旋律は深く歌って下さい!
高校教員Y
部門:高等学校(14人)
本番までの練習時間:3ヶ月
。 速いパッセージなどはあまり多くないのですが、Tuttiで瞬発力の求められる場面が多いので、サウンド感の統一やバランス調整が重要になってくると思います。また、楽曲の雰囲気が目まぐるしく変化するため、それぞれの場面の音の扱い方をどうするかもしっかり考えられると素敵な演奏になると思います。
最後に登場するCantabileの旋律はとても感動的です。
イフィシャル
部門:その他(4人)
本番までの練習時間:-
1曲目では、各人が何をやっているのか譜読みが大変ですので、初回練習時には、スコアを皆で見ながら取り組むと良いでしょう。
実は、同じ旋律を誰かが繋いでいるので、それを頼りにしてください。
静かな曲ですが、その分、各人の基礎の実力がはっきりと表れてしまいます。
2曲目では、当たり前のことですが、まずは主旋律をイメージしてください。
各人がそれぞれ「忙しい箇所」と「伴奏となって支える」場所があります。
主旋律をイメージしながら演奏しないと、聞かせたいメロディが聞こえなくなってしまいますので、注意してください。
3曲目は、とても有名ですが、4曲中ではこの曲が一番、地道な練習が必要です。
意外と拍子の頭が揃わない箇所が多いので、まずは6/8拍子を意識して、縦を正しく合わせられる様になってから少しずつテンポを早めると良いでしょう。
練習時に、「なんか違和感あるな?」と思ったら、一度ゆっくり合わせられるようにしてください。
4曲目では、♯が多く、4曲中最も忙しい曲ですが、「大変である」ことを絶対に聞かせてはいけません。
まずは、軽やかに演奏できるように臨みましょう。
理想的には、合わせる前に暗譜しているくらいやり込んでおいたほうがいいです。
チューナーやメトロノームも大事ですが、この曲ではそれだけに頼っていると、この曲の雰囲気が出せません。
4曲とも、「昔から今まで、人々によって伝えられてきた曲」なのですから、感情を豊かにして合わせられるように取り組んでください。
石切のてらえもん
部門:中学校(45人)
本番までの練習時間:4ヶ月
k
部門:高等学校(30人)
本番までの練習時間:3ヶ月
R.F
部門:高等学校(16人)
本番までの練習時間:5ヶ月
Aからのメロディーは装飾音しっかりと息を入れると民族音楽らしい雰囲気が出ると思います。
練習番号Cからはクラリネットに8分音符と刻みの8分音符のラインが乱れやすいので、一度全員タンギング(普通の長さ)にして練習をしてから各自のアーティキュレーションに戻すと良いと感じました。42小節目からのトロンボーンのメロディーはフレーズが短くなりがちなので、練習番号Dの前の木管楽器に受け渡す4小節のフレーズを意識すると良いと思います。(この辺りの歌い方は実際に映画を見て、歌詞がわかると自然とそうなると思います。)
練習番号DからはDとGの音による下降系(または逆行系の合いの手)を主体としたメロディーです。どちらも低い音に重心がいくようにD、Gを四分音符に直して同じ音量、音質で吹けているかの確認をして曲の練習に入ることが大切だと思います。 練習番号Fからの木管楽器の連符ですが、難しい場合は分業が良いと思います。68小節目からのトランペットのメロディーはその下の二分音符のスピード感を意識しながら練習すると良いと思います。
練習番号Hからは是非映画で確認していただきたいのですが、メロディーを歌っているキャラクターと場面が移り変わっていくシーンです。
ですので、その辺りを念頭におきながら、強弱や奏法を考えていくと良いと思います。また、この辺りから強奏部が続きますので、設計をよく考えながら練習を進めていくと良いと思います。
練習番号Lからですが、まず意外と早いです。この辺りの和音は比較的わかりやすいので、生徒同士でも練習が進められると思います。
また、練習番号Oからのメロディーの吹き方やテンポ設定は映画のラストシーンを参考にすると良いと思います。(映画は意外とあっさりしてます)
練習番号Qからは映画では歌を伴って演奏される場面です。歌がある部分と楽器だけの所で、音の長さや吹き方が変わっているので参考にされると良いと思います。
エンディング部は映画よりも3小節長くなっているので、特に金管楽器のペース配分には気をつけた方が良いと思います。
T.U
部門:中学校(19人)
本番までの練習時間:3ヶ月
妖精の国のピアノパートは、広い音域、強い音量でのグリッサンドがあります。指や爪を壊さないように、プラスチックの消しゴムを使うと楽になります。本番は・・・?笑
こう
部門:中学校(30人)
本番までの練習時間:4ヶ月
この曲は全体的に山型アクセントと普通のアクセントの区別をしっかりつけないとウルサイだけの音楽になってしまい、曲の魅力や雰囲気が伝わらないと思います。
6/8拍子の部分はしっかり拍感を出せると良いと思います!
ゆったりとした叙情的な旋律はしっかり歌い込めると、金管主体のファンファーレとの対比が出て印象的になると思います。 打楽器もしっかりと細かなリズムを揃えてあげられるといいと思います。
高橋先生の作品らしく、親しみやすい曲なので、中学生の部員たちと楽しく練習でき良い結果も残せた思い出の曲です。 金管が少ないと少し厳しい曲かと思いますが、是非チャレンジしていただきたい1曲です。
Nerima Brass Players
部門:―
本番までの練習時間:5日
https://youtu.be/FGdIdL2spo4
Y.T
部門:中学校(45人)
本番までの練習時間:5ヶ月
フラヴィア
部門:(41人)
本番までの練習時間:5ヶ月
・全体的な印象として、フルートパートに十分な技量と豊かな音量が要求されます。
・ドビュッシー自身による管弦楽編曲に対し、この楽譜は忠実にアレンジされているので、管弦楽版の録音を聴き込んで研究し、ドビュッシーが作りたかった響きのイメージを練り上げていくのが良いと思います。
・練習番号2の10小節目からの主題は、オーボエとミュート付きトランペットとの音量バランスをうまくコントロールできると、本当にバグパイプのような響きを得ることができます。
・ピアノやピアニッシモ指示が多いのですが(すべてドビュッシーによる原譜通り)、楽想に応じて適宜音量を調整しながら演奏する方が良いと思います。音量記号はバンド全体での強音、または他の音量の大きな部分との対比として相対的に捉えるべきだと思います。
・練習番号9からのアルトサックスソロは、原曲がコーラングレーのソロであることを踏まえ、ヴィブラートは控えめに、dolceに演奏するのがベターだと思います。
・ピアノからクレッシェンドして、その行き着く先が「ピアノ」の音量指定である場合が多々ありますが、記譜の誤りではありません。音量をぐんぐん膨らましてからの弱音表現というのはドビュッシーらしさの発露でもありますので、工夫して演奏して頂ければと思います。
M.S
部門:高等学校(13人)
本番までの練習時間:9ヶ月
13名でも共鳴する『ツボ』を見つけるまで、片岡先生と探究の日々でした!
練習曲「スムーズ・アンド・クリスピー」の後半部分を用いて、全身を使って速い息、音圧の高い息をコントロールして生み出すトレーニングを日々取り組んでいました。
当時の1・2年生を連れてワゴン車で新潟へ行き、アンサンブルコンテスト西関東大会で初演団体の川口市・アンサンブルリベルテ吹奏楽団の演奏を鑑賞しました。演奏形態は異なるものの上手な大人バンドの演奏を聴いた体験は、その後の音作りによい影響を残しました。
どんなサウンドにしたいか、自分たちのバンドの指向性に近い上手なバンドの生演奏はよい刺激になります。
冒頭のVib. solo は、ペダルを踏みっぱなしだと音が濁ります。「ミュート奏法」(是非、教わるか、調べてください)で、スッキリとしたサウンドにするとよいです。因みに他の片岡作品(「鳥之石楠船神」等)のVib. soloでも効果があります。 [N]Free Styleの部分は、元々、楽器の持ち替えの時間を稼ぐための即興演奏として後から追加した部分です。練習していく中で、『砂漠に吹く風』というイメージになりました。ペルセポリス遺跡やペトラ遺跡などの映像を見てイメージを膨らませてみてはいかがでしょうか?
[P]のTp. soloは、Off stageで演奏すると、ピッチが下がって聴こえる場合があります。注意してください。 [R]-[S]-[T]-[U]は、『キャラバンの行列』、『市場の賑わい、群衆』のイメージです。原曲の管打楽器8重奏版にはない場面の一つです。ダラブッカを買ってきたので、ダラブッカに似合う部分を作曲してください!と片岡先生に頼み込んで、加筆してもらいました。生徒の前で片岡先生が鼻歌を歌った後、片岡先生のピアノにあわせて生徒が聴音、最後に楽譜にするというとても貴重な体験をしました。反面、常に修正が入る部分になってしまい東日本大会の直前まで修正が入ったので、創作の楽しみと満足いくまで仕上げる苦労の両方がありました。出版の際にさらに修正が入ったようです。グループごとに音楽が進行していくので、まずは誰と誰がどこからどこまで同じグループであるかを理解しておく必要があると思います。126小節目?は、それぞれのグループが熱狂的に加速していきます。独立したいたはずのそれぞれのグループが一気に集合してくる情景を表現してみてください。
ダラブッカは4万円前後の楽器を購入しました。大編成バンドだともう少し価格が高く大きいタイプのダラブッカの方が音量がててよいかもしれません。当初、ダラブッカよりも安いジャンベでいいかなと考えていましたが、東京の某打楽器専門店で店員さんにジャンベとダラブッカを叩いてもらい聴き比べたところ、ジャンベはやっぱりアフリカでした(笑)
打楽器の生徒にダラブッカを預け、最初の1ヶ月はYouTube等を見て自己流で叩いていました。ある日、インターネットで検索したところ、地元でダラブッカのワークショップを開いている方を見つけました。4月下旬に打楽器の生徒をワークショップに送り出し、それ以降は月1回程度でレッスンをお願いいたしました。左手の使い方を覚えてしまえば、それなりの打楽器経験のある人ならば、思ったより習得に時間が掛からないと思います。難しい場合は、ジャンベのように股に挟み込んで打面を水平にして叩くのもありだと思います。地元にダラブッカ奏者がいないか一度調べてみるとよいと思います。「ダラブッカ」で見つけられない場合は、「ベリーダンス」を検索してみてください。ベリーダンス教室で伴奏の仕事していることもあるそうですよ。 132小節目?のダラブッカ soloは、記譜上、2音(ドゥムとテック)のみなっていますが、カやパの音を入れてもよいと思います。
個性的でアクの強く、アクロバティックな曲なうえ、全ての楽器に見せ場があるように作曲していただきました。尚更、陸上自衛隊音楽隊による参考演奏を聴くとハードルが高いと感じるかもしれませんが、先を考えて地道に取り組めば、きっといい結果に結びつきます。私達が演奏した13名の内訳は、3年生2名、2年生6名、1年生5名でした。長いsoloを演奏したob.とcl.の生徒はどちらも1年生で、2人とも入学当初は、正直、標準的な中学生以下でした...2人ともごめんさい m( _ _ )m ただ、毎日毎日、少しずつ少しずつ、夏に向けて努力してくれました。そのお陰で、秋に金沢で演奏することができました。ありがとう!!
小編成バンドは、ロー・グレードではないですし、大編成バンドのダウンサイジングでもありません。個々のバンドのカラーを独自のサウンドで表現できます!! 大編成バンドにはないアプローチがあるはずです!! どうか自分達のバンドのサウンドと音楽をとことん追究してみてください!!
R.F
部門:高等学校(24人)
本番までの練習時間:4ヶ月
練習番号Cのマリンバソロは、カデンツのように自由に演奏した方が良いと思います。練習番号Gからの木管楽器とマリンバに現れる連符ですが、揃えるというよりは絶え間なくなっている感じを作っていくことが大事だと思いますので(特に5連符が始まると揃えることがさらに難しくなるので)ブレスの位置を工夫する、演奏する奏者や箇所(例えば1拍目と3拍目だけ吹く奏者と2拍目、4拍目を吹く奏者を分ける)などの工夫が考えられます。また金管楽器を主体としたハーモニーの刻みがありますが、人数が少ない場合でもなるべく全ての音が鳴っていた方が効果的だと思いますので、パートの置き換え等の工夫があると良いと思います。
練習番号Jからの木管楽器の音列による練符は初心者の生徒でも演奏可能なので、ゆっくりでも複数人いると効果的です。 またここからは打楽器がかなり目立つので、欠けているパートがあれば管楽器奏者などで補うと良いと思います。
終結部ですが特に最後の2小節は、どのくらいやるかの事前計画が必要だと思います。打楽器のクレッシェンドが行き過ぎてしまうと、音楽全体を壊してしまう原因にもなりかねないので、注意しながら練習を進めていくと良いと思います。最後の小節は個人的には一度切って取り直した方が、エンディングとしてふさわしいのではないかと感じています。
S.Y
部門:高等学校(21人)
本番までの練習時間:4ヶ月
楽章が5楽章あり、その中でもスペインの踊り、第一幕 ヴァリエーションⅠ、ギャロップを選び練習いたしました。 スペインの踊りでは、なかなか木管の旋律と、その他の楽器の伴奏とでテンポの感じ方があわず、とても苦労をしました。そのためスペインの踊りをライモンダだけでなく、他のバレエ音楽の中の映像をYouTubeで探して生徒たちと見て、様々なバレエの踊りからヒントを得て、自分たちなりに考えていくうちに気持ちがまとまり、テンポがあってきたのを今でも思い出します。 第一幕 ヴァリエーションⅠでは、どれだけ可愛らしさが出るかを考えて演奏しました。初めはピアノでチェレスタの部分を演奏していたのですが、どうしても曲の世界観が出なかったため、夏休みに入り急遽、チェレスタをお借りしコンクールに出ました。ただそこまでこだわったお陰か、とても良い演奏だったと褒めてもらえたのを今でも覚えています。なので無理のない範囲で、用意できるのであればチェレスタを用いて演奏することをお勧めいたします。
最後にギャロップですが、ここでも木管の旋律と他の楽器の伴奏とで合わせるのに苦労しました。特にですが、繰り返し出てくるテーマに生徒たちは指が回らなかったりと苦労していました。ただ、ゆっくりから練習していくうちに慣れていき、できるようになっていったのを覚えています。諦めて雑になっていた時もありましたが、やればやるほどできてきたのを体感したようで、最後コンクールでは楽しそうに演奏していました。さらにその後にある、オーボエのソロ(私がやった時はフルートでやりました)、クラリネットのソリの部分を仕上げるのが一番この曲の難所でした。ただ、奇跡的に音大を目指していたクラリネットの子がいてその子に釣られて他の子も上手になり難を逃れました。こういう子がいなかったらと思うと今でもゾッとします。 最後に人生の中で1度しかない学校生活、その貴重な1年をこの曲とともに一緒に過ごせたことを生徒ならびに関係者の方々にとても感謝してます。
T.M
部門:-
本番までの練習時間:4ヶ月
にんじん
部門:中学校(20人)
本番までの練習時間:8ヶ月