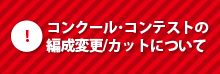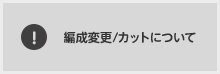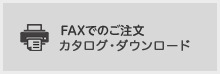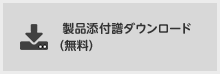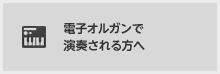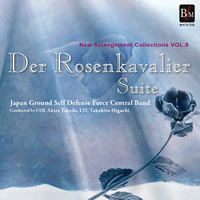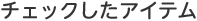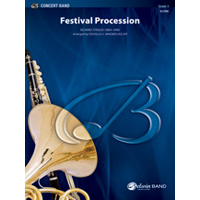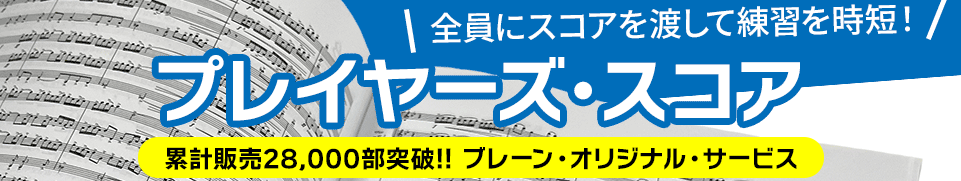
宅配スコア閲覧
楽曲詳細情報
- 作曲
- ジャコモ・プッチーニ(Giacomo Puccini)
- 編曲
- 後藤 洋(Yo Goto)
- 演奏時間
- 7分00秒 (約)
- グレード
- 5
- 主なソロパート
- 特になし
- Trp.最高音
- 1st:As / 2nd:Es / 3rd:B♭
- 編成
- 吹奏楽
楽器編成
- Piccolo (doub. Flute 3)
- Flute 1 & 2
- Oboe 1
- Oboe 2 (doub. English horn)
- Bassoon 1 &2
- E♭Clarinet
- B♭Clarinet 1 , 2 & 3 (all div.)
- Alto Clarinet
- Bass Clarinet
- Contra-alto Clarinet
- Soprano Saxophone
- Alto Saxophone 1 &2
- Tenor Saxophone
- Baritone Saxophone
- Trumpet 1 (doub. Flugel horn)
- Trumpet 2 & 3
- Horn 1 , 2 , 3 & 4
- Trombone 1 , 2 & 3
- Euphonium (div.)
- Tuba (div.)
- String Bass (div.)
- Harp
- Celesta & Piano
- Timpani
- Percussion ※4 players~
- Snare Drum
- Large Snare Drum
- (or Field Drum)
- Bass Drum
- Crush Cymbals
- Suspended Cymbal
- Tam-tam
- Crotales (opt.)
- Glockenspiel (opt.)
- Vibraphone
- Marimba
- Chimes
楽曲解説
この作品は2010年、石川県の金沢市立工業高等学校吹奏楽部(顧問:幸正勤也氏)の依頼により、コンクール自由曲として編曲されたものです。
ジャコモ・プッチーニ(1858-1924)の代表作のひとつである《トスカ》は、ヨーロッパが政治的変革の最中にあった1800年6月のローマを舞台としています。全3幕からなる歌劇で、主な登場人物は共和主義者の政治犯アンジェロッティと、その同志の画家カヴァラドッシ、カヴァラドッシの恋人の歌姫トスカ、そして王制ローマで警視総監として共和主義者を弾圧し、トスカに横恋慕するスカルピアの4人です。
アンジェロッティをかくまったカヴァラドッシが捕えられ、それを助けようとするトスカがスカルピアを刺し殺してしまう第2幕も、そして処刑されたカヴァラドッシを追ってトスカ自らも身を投げる第3幕も、それぞれに劇的で美しい旋律に溢れていますが、吹奏楽のためのこの編曲では、4人の登場人物のキャラクターとその関係が立体的に描かれ、冒頭で響く基本主題を軸にオーケストラが最も雄弁にドラマを主導する、すなわち演劇と音楽の両面で最も「交響的」な第1幕にポイントを絞り、そのドラマを約7分に要約して表現することをこころみました。
全体は以下の5つの場面から構成されています。【1】歌劇の導入部,【2】トスカとカヴァラドッシの2重唱(シーン5,この編曲では[A]~[C]),【3】脱獄してきたアンジェロッティがカヴァラドッシと教会で再会する場面(シーン4,[C]~[E]),【4】スカルピアに嫉妬心をあおられたトスカの嘆き(シーン9,[E]),【5】教会に集まった人々が歌うテ・デウムとスカルピアの独白(第1幕フィナーレ,[F]~)。これらの場面は幸正勤也氏と編曲者が討議を重ねた結果選ばれたものですが、主要な登場人物がそれぞれ中心となる場面を設定し、さらにコンサート・ピースとして独立できるような構成を目指しています。
プッチーニは非常に綿密にアーティキュレーション(特にアクセントとスタッカート)の指示を書き込んでいますので、この編曲でもそれらをできるだけ尊重するように努めました。音符以外の記号や指示の意味を探求することは、より説得力のある演奏へ近づくための大きな手がかりになるでしょう。また、ゆっくりとした場面が多いので、音楽の流れが停滞しないようにフレージングへの十分な配慮を怠らないようにしたいものです。
「テ・デウム」の鐘と大砲の響きは、打楽器とピアノの音色を組み合わせて作っていますが、楽器の選び方やバランスについてはそれぞれの演奏団体の工夫を期待します。教会に人々が終結して神を賛美することの意味、そこに大砲の音が響く意味を考えることで、場面にふさわしい音色がおのずから決定されるのではないでしょうか。
(後藤 洋)