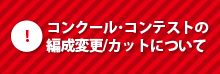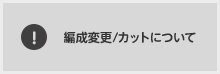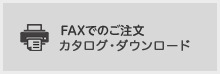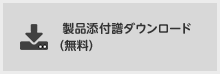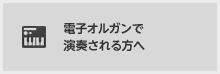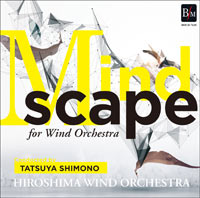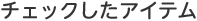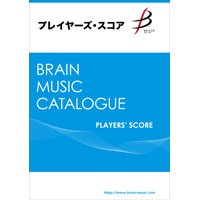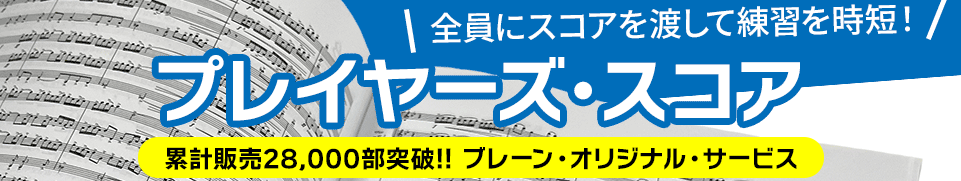
宅配スコア閲覧
楽曲詳細情報
- 作曲
- マヌエル・デ・ファリャ(Manuel de Falla)
- 編曲
- 森田一浩(Kazuhiro Morita)
- 演奏時間
- 20分00秒(約)
1.序奏~昼下がり (2:30)
2.粉屋の女房の踊り (2:40)
3.隣人たちの踊り (3:30)
4.粉屋の踊り (3:00)
5.終幕の踊り (6:00) - グレード
- 5
- 主なソロパート
- Fl. / Ob. / E.Hrn. / Bsn. / B♭Cl. / Hrn.
- Trp.最高音
- 1st:A / 2nd:Fis/ 3rd:Fis
- 編成
- 吹奏楽
楽器編成
- Piccolo
- 1st & 2nd Flutes
- 1st Oboe
- 2nd Oboe
- (doub. English Horn in F)
- 1st Bassoon
- 2nd Bassoon
- (doub. Contrabassoon)
- Clarinet in E♭
- 1st Clarinet in B♭ (div.)
- 2nd Clarinet in B♭ (div.)
- Alto Clarinet in E♭
- Bass Clarinet in B♭
- Contrabass Clarinet in B♭
- Soprano Saxophone in B♭
- 1st Alto Saxophone in E♭
- 2nd Alto Saxophone in E♭
- Tenor Saxophone in B♭
- Baritone Saxophone in E♭
- 1st Trumpet in B♭
- 2nd Trumpet in B♭
- 3rd Trumpet in B♭
- 1st & 2nd Horns in F
- 3rd & 4th Horns in F
- 1st Trombone
- 2nd Trombone
- Bass Trombone
- Euphonium (div.)
- Tuba (div.)
- String Bass
- Piano (doub. Celesta)
- Harp
- Timpani
- Percussion
- Snare Drum
- Bass Drum
- Crash Cymbals
- Suspended Cymbal
- Tam-tam
- Triangle
- Tambourine
- Castanets
- Glockenspiel
- Xylophone
- Vibraphone
- Marimba
楽曲解説
19世紀スペインの作家、アラルコンの短編小説を原作とするバレエ《三角帽子》は、マヌエル・デ・ファリャ(1876-1946)の舞台音楽のなかでもひときわ高い評価を得た作品であろう。スペイン南部のカディスに生まれたファリャは、初めマドリード音楽院でピアノを学び、ピアノ奏者として活動した。このころ、のちに“スペイン国民楽派の父”とも呼ばれた作曲家、音楽学者のペドレルに作曲を師事したことで、ファリャはスペインの民俗音楽に開眼したとされている。
《三角帽子》は、当初パントマイム《代官と粉屋の女房》の付随音楽として書かれたのち、ロシア・バレエ団の主宰者、ディアギレフの求めに応じてバレエ作品に改編され、1919年にロンドンで初演された。バレエは、ある日の「午後」と「夜」の出来事を描いた2つの部分からなり、主要曲を抜粋した2つの演奏会用組曲もしばしばコンサートでとりあげられる。この吹奏楽編曲は、組曲に含まれる特徴的な舞曲を中心にさらにコンパクトな組曲にまとめたもので、以下の5つの楽曲で構成されている。
1.序奏-昼下がり ティンパニに導かれて、トランペットとホルンがファンファーレ風な音型を演奏する「序奏」(編曲では1コーラスに短縮)に続き、もの憂い雰囲気の「昼下がり」で第1部の幕が上がる(当該曲の後半部分を使用)。
2.粉屋の女房の踊り 物語の主要登場人物でもある粉屋の女房の、情熱的な踊り。アンダルシアの代表的な民俗舞踊、ファンダンゴのスタイルが使われている(編曲では、コーダとして第1部の終結部を使用)。
3.隣人たちの踊り 第2部冒頭の音楽で、聖ヨハネ祭を祝う村人たちの踊り。これもアンダルシアの民俗舞踊のひとつである、セギディーリャスのスタイルで書かれている。
4.粉屋の踊り 勇壮なホルンの信号、イングリッシュ・ホルンの“こぶし”を思わせる音型に続き、即興性にあふれた男性的なファルーカが踊られる。ファルーカはスペイン北部のガリシア地方に起源があるとされる舞踊で、フラメンコのジャンルのひとつとして広く知られるようになった。ギターで演奏されることが多く、ここでもギターのラスゲアード奏法(指の爪で弦をかき鳴らす奏法)を思わせるリズムが現れる。
5.終幕の踊り 物語を締めくくる第2部最後の踊りで、大団円に向かってさまざまな展開がくり広げられる。主要テーマには、スペイン北東部を起源とするホタのスタイルがとり入れられ、華やかな旋回舞踊風の雰囲気をつくり出している。
当初は民俗舞曲的な楽曲を抜粋するつもりで編曲を始め、原曲の第1部からは「粉屋の女房の踊り」のみを選んでいたが、あまりにも勝手な選曲のように思われ、それで「序奏?昼下がり」を冒頭に加えることにした。結果的には、部分を抽出して演奏する際の選択肢が増えたように思われる。第1、2曲のカットに関してはオーケストラのさまざまな演奏を参考に、実例のあるカットを導入した。なお演奏会用第2組曲にあたる第3~5曲は、原曲どおりのサイズでカット部分はない。
(森田一浩)