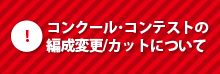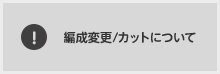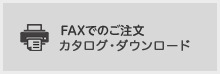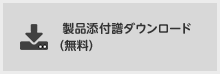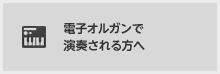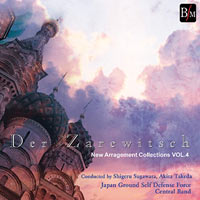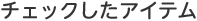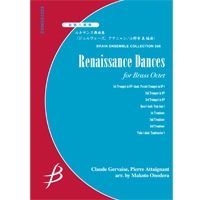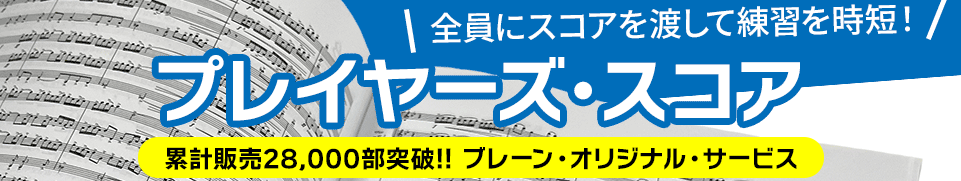
宅配スコア閲覧
楽曲詳細情報
- 作曲
- ヨハン・ゼバスティアン・バッハ(Johann Sebastian Bach)
- 編曲
- 田村文生 (Fumio Tamura)
- 演奏時間
- 8分00秒 (約)
- グレード
- 4.5
- 調性
- 原調 (Es:)
- 主なソロパート
- Picc.(opt.) / Fl. / Ob. / A.Sax.
- Trp.最高音
- 1st:G / 2nd:E / 3rd:Es
- 編成
- 吹奏楽
楽器編成
- Piccolo
- Flute 1 & 2
- Oboe 1
- Oboe 2
- (doub. English Horn opt.)
- Bassoon 1 & 2
- E♭Clarinet
- B♭Clarinet 1 , 2 & 3
- Alto Clarinet
- Bass Clarinet 1 & 2
- Contra-alto Clarinet
- Soprano Saxophone
- Alto Saxophone 1 & 2
- Tenor Saxophone
- Batione Saxophone
- Trumpet 1 , 2 & 3
- Horn 1 , 2 , 3 & 4
- Trombone 1 , 2 & 3
- Euphonium (div.)
- Tuba
- String Bass
- Timpani
- Percussion ※5 players~
- Snare Drum
- Bass Drum
- 3 Tom-toms
- Crash Cymbals
- Suspended Cymbal
- Hi-hat Cymbal
- Tam-tam
- Triangle
- Tambourine
- Castanets
- Glockenspiel
- Xylophone
- Chimes
楽曲解説
音楽史上最大の偉人のひとりで、音楽の父と呼ばれたヨハン・セバスティアン・バッハ(1685-1750)は、その旺盛な作曲・演奏活動によって、オルガン曲、管弦楽曲、器楽曲、宗教声楽曲、世俗声楽曲のどの分野においても質の高い作品を数多く残し、ドイツのバロック音楽を集大成して、後の世代に多大な影響を与えたことで広く知られています。
自身がオルガンを始めとする鍵盤楽器の名手であったバッハは(その見事な即興演奏の腕前は有名でした)、この分野にも優れた作品を数多く残し、オルガンのための「前奏曲とフーガ」だけでも20曲以上書いています。
このBWV552の変ホ長調の前奏曲は、その中でも特にスケールが大きく、その力強く壮麗な楽想、変化に富んだ構成(トッカータ、フランス風序曲、協奏曲など、様々な様式が混合して用いられています)は、管弦楽や吹奏楽による華麗な編曲に適した内容を持っていると言えるでしょう。大編成のシンフォニー・オーケストラの特徴を見事に生かしたシェーンベルクの編曲は、特に有名な存在となっています。
【吹奏楽版について】
福島東高等学校の委嘱により編曲され、2001年8月喜多方プラザ文化センターにおいて、同校により初演。
この編曲は、オルガンのための「前奏曲とフーガ」BWV552の前奏曲部分ですが、原曲をほとんどそのまま残しつつも、以下の点において様々な「脚色」が加えられています。それは先ず、打楽器の扱いです。
例えば吹奏楽に限定してみても「バッハの編曲」におけるこれまでの打楽器というものは、管楽器の旋律や和声に色彩を効果音的に加えるというような範疇に留まっていたかのように思えます。しかしこの編曲では、そのような慣用的書法も採用しつつ、打楽器の音色・リズムが合奏全体をアーティキュレートするような状態を形成することも目的とし、打楽器が積極的に音楽全体に侵入してゆくことによって、楽曲構成をも支配する機能を持たせています。その点においては、原曲の音の並びをほとんど変えないながらも、打楽器パートによる新たな響きを付加しつつ、結果的には音楽的起伏の転換すら図っている部分があります。
しかし一方、一見して原曲と非常にかけ離れた箇所も存在します。それは、モティーフの繰り返しの多用によって、ともすればメカニカルな側面が目立つ原曲の旋律・リズムを、一時的に大きく崩しながら歌謡的(歌唱的)、また逆にトッカータのような急速で装飾的なものに変化させるといった、様式的模倣によって原曲を変質させた部分です。しかし、そのように原曲から非常にかけ離れた状態においてさえも、それ以外の要素、例えば和声や旋律の大まかな運動に関しては原曲と殆ど変わりません。
このような作業を経ると、編曲における「原曲との距離感」ということが少なからず意識されてきますが、過剰なまでにデフォルメされている部分を含め「編曲」に関する私の見解として理解して頂いて良いと思います。
演奏に際しては、様々な旋律の形を明瞭にし、声部の独立性を保持しつつ、絡み合いを音楽化して下さい。フレーズの歌い方は勿論、少し大きな枠での演奏構成を必要とすると思います。また、打楽器の瞬間的な独奏(音符1個だけのソロさえ)では、合奏全体に対峙できるクオリティー(音量、アーティキュレーション)を心がけて下さい。原曲を「変調」させている度合いの強い編曲だと思いますので、演奏面においても「過激さ」が望まれます。
(田村文生)