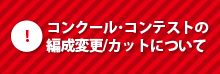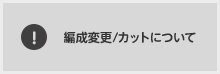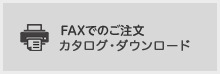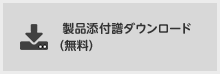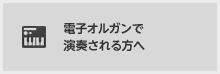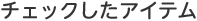楽曲詳細情報
- 作曲者
- ジョン・マッキー(John Mackey)
- 演奏時間
- 9分00秒 (約)
- グレード
- 6
- 編成
- 吹奏楽
- 主なソロパート
- Cl. / S.Sax.
- Trp.最高音
- 1st:high H / 2nd:As / 3rd:G / 4th:As
- 出版社
- オスティ・ミュージック(Osti Music)
楽器編成
- Picc.
- Fl.1&2
- Ob.1&2
- Eb Cl.
- Cl.1,2&3
- B.Cl.
- Bsn.
- Contra Bsn.
- S.Sax.
- A.Sax.1&2
- T.Sax.
- B.Sax.
- Trp.1,2,3&4
- Hrn.1,2,3&4
- Trb.1&2
- Bass Trb.
- Euph.
- Tuba
- St.Bass
- Timpani
- Perc.1
- Hi-hat
- 2 T-toms
- Splash Cym.
- China Cym.
- Perc.2
- B.Dr.
- Brake Dr.
- Finger Cym.
- T-tam
- Perc.3
- 4 T-toms
- Brake Dr.
- Sus.Cym.
- Xylo.
- Glock.
- Vib.
- Mari.
- Piano
- Harp(Opt.)
楽曲解説
エモリー大学のS.スチュワート氏とラマー大学のS.ヴェイス氏が主催する大学協会からの委嘱によって吹奏楽版に編曲されました。吹奏楽版の初演は、S.スチュワート氏指揮によるエモリー大学ウインドアンサンブルによって、2004年2月26日に行われました。
もともとは、ブルックリン・フィルハーモニックの委嘱によるオーケストラ作品で、2003年2月にブルックリン音楽アカデミーでK.イエルビィ氏の指揮によって世界初演されました。この作品はそれを吹奏楽版に作り直したもので、私にとっては初の吹奏楽作品となります。その後この吹奏楽版は世界中で100回以上演奏されています。2004年にウォルター・ビーラー記念作曲賞、2005年にはABAオストワルド賞をそれぞれ受賞しています。
「レッドライン・タンゴ」は2通りのタイトルの由来があります。1つ目は、よく使われる言葉「redlining an engine(回転計)」のredline(レッドライン)です。これはエンジンが最大限まで回転するという意味です。2つ目は、ニューヨークのIRT地下鉄路線、2番線と3番線の「red line(レッド・ライン)」です。この路線は私のマンハッタンのアパートと、この作品の初演が行われたブルックリン音楽アカデミーの間を走っています。
この曲は3つの部分に別れています。1番目のセクションはまさに「redlining(エンジンが最大限に回転する)」の部分です。16分音符の動きによって常に走り続けながら、徐々に激しさを増していきます。その頂点をすぎると2番目のセクションである「タンゴ」が始まります。「タンゴ」はやや軽快かつ滑稽で、けだるさすら感じられます。「タンゴ」の構成要素は最初のセクションから引き継がれています。さらに曲想は変化して3番目のセクションに移行します。この部分では、最初のセクションの曲想がさらに激しさを増していき、最後ははじけるように幕を閉じます。
(ジョン・マッキー)
※2005年ABAオストワルド賞 受賞
※2004年ウォルター・ビーラー記念作曲賞 受賞