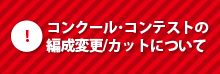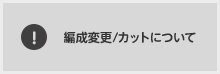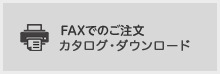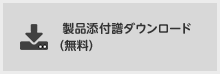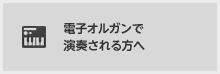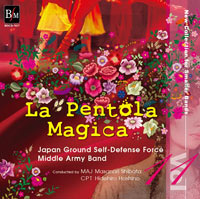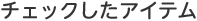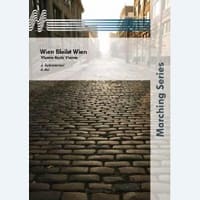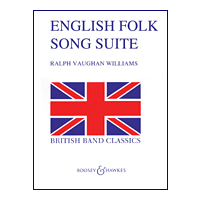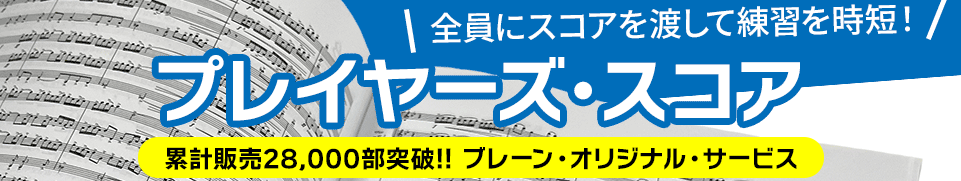
宅配スコア閲覧
この曲は元々、12名程度のバンドのために書かれた曲なので、スコアに書かれた編成通りでなくても演奏可能ですし、ピアノやハープなどオプション楽器も豊富なので、色々な工夫ができると思います。また、途中の女声合唱の部分は、もちろんメンバーが歌っても良いのですが、コンサートなどでは合唱部とのコラボにするとステージが華やかに見えますよね。曲想も変化に富んでいるので、コンサートには特におススメだと思います。 (都賀城太郎)
楽曲詳細情報
- 作曲
- オットリーノ・レスピーギ(Ottorino Respighi)
- 編曲
- 小野寺真 (Makoto Onodera)
- 演奏時間
- 7:00(約)
- グレード
- 3.5
- Trp.最高音
- 1st:high B♭(A) / 2nd:F
- 主なソロパート
- Fl. / B♭Cl.
- 最少演奏人数
- 21名
- 編成
- 吹奏楽(小編成)
楽器編成
- 1st Flute
- (doub. Piccolo)
- 2nd Flute (opt. div.)
- Oboe (opt.)
- Bassoon (opt.)
- Clarinet in E♭ (opt.)
- 1st Clarinet in B♭(opt.div.)
- 2nd Clarinet in B♭
- Bass Clarinet in B♭
- Alto Saxophone
- Tenor Saxophone
- Baritone Saxophone
- 1st Trumpet
- (doub. Flugelhorn)
- 2nd Trumpet
- 1st Horn in F
- 2nd Horn in F
- 1st Trombone
- 2nd Trombone
- Euphonium
- Tuba
- String Bass (opt.)
- Piano (opt.)
- Harp (opt.)
- Female Chorus
- Timpani
- Marimba
- Sleigh Bells
- Triangle (opt.)
- Suspended Cymbal (opt.)
- 1st Percussion
- Glockenspiel
- Marimba
- Xylophone
- Suspended Cymbal
- Bass Drum
- 2nd Percussion
- Vibraphone
- Xylophone
- Snare Drum
- Suspended Cymbal
- Marimba
- Triangle
- Glockenspiel
- Crash Cymbals
- 3rd Percussion(opt.)
- Glockenspiel
- Triangle
- Snare Drum
- Xylophone
- Vibraphone
- Suspended Cymbal
- Bass Drum
楽曲解説
1920年にローマで初演されたバレエ。ロシアを舞台としており曲の随所にロシア民謡が使用されている。
バレエの大まかなあらすじは以下の通り。
「あるわがままなロシアの姫は、若い王子と結ばれることを夢見ている。ある日、退屈で時間をもてあましている姫のために、様々な催しが催されていた。そんな中、ある農夫が「魔法の鍋」だという鍋を持参してその周りで踊り、姫はその踊りに魅了されてしまう。どうしてもその鍋がほしいと言う姫に農夫は姫のキスを要求。最終的にその要求を姫が断ると、農夫は自身が王子であることを明かし、姫は涙する。」
この吹奏楽用編曲は埼玉県・川越市立野田中学校(顧問・森仁美先生)の委嘱で2017年に編曲、今回の録音と出版に際し加筆、訂正を加えた。
全曲の中から4曲を選び、それぞれの曲も短縮されている。ハイライトのような形で様々な性格のシーンを楽しめるよう、またコンサートやコンクール等で演奏しやすいよう構成した。
【演奏上の注意】
1、楽譜に記されているメトロノーム速度表記は編曲者が記入したもので、レスピーギ自身が書いたものではない。目安として参考にしていただきたい。
2、打楽器はマレットが指定されていることがあるが、メーカーや種類によって編曲者が意図した音色とは大きく変わってしまうことも考えられる。原曲の音源や編曲者の指示を参考に、「何故そのマレットを指定しているか」を考慮した上で最適なマレットを選択していただきたい。
3、ピアノ及びハープは両楽器ともオプション扱いだが、「コサックの踊り」冒頭部分や「アルメニアの歌」はどちらか片方の楽器は入ることが望ましい。
4、「アルメニアの歌」では女声合唱パートが2パート入っているが、バンドの人数事情によっては1パートのみ、又は合唱を入れられないことも予想される。
その場合、合唱が無くても演奏できるよう編曲しているが、メロディーを演奏しているパートの音量を上げたり人数を増やすなど、適宜調整をしていただきたい。