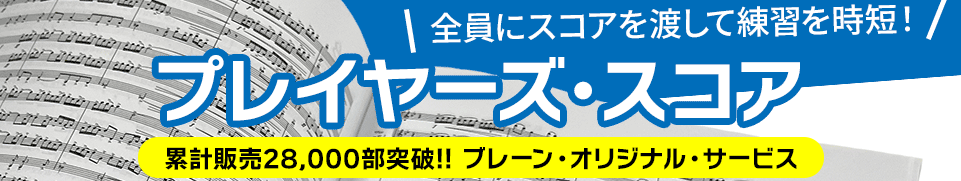
チャッコーナ・アラルガータ ~パルティータ第2番 BWV.1004 より/J.S.バッハ(田村文生)【吹奏楽ライセンス楽譜】

- 在庫
- 在庫あり
- 商品コード
- YDAB-B08
- メーカー
- ブレーンミュージック / Brain Music
宅配スコア閲覧
宅配スコア閲覧:チャッコーナ・アラルガータ ~パルティータ第2番 BWV.1004 より/J.S.バッハ(田村文生)
楽曲詳細情報
- 作曲
- J.S.バッハ(Johann Sebastian Bach)
- 編曲
- 田村文生(Fumio Tamura)
- 演奏時間
- 11:40
- グレード
- 5.5
- 主なソロパート
- E.H.(A.Sax.) / Cl. / A.Sax.
- Trp.最高音
- 1st:High B♭ / 2nd:G / 3rd:F♭
- 演奏最少人数
- 36~
- 編成
- 吹奏楽(大編成)
- Piccolo (doub. Flute)
- 1st Flute
- 2nd Flute
- Alto Flute in G (option)
- 1st & 2nd Oboes
- English Horn in F
- 1st & 2nd Bassoons
- Contrabassoon (option)
- Clarinet in E♭
- 1st Clarinet in B♭
- 2nd Clarinet in B♭(div.)
- 3rd Clarinet in B♭(div.)
- Alto Clarinet in E♭(option)
- Bass Clarinet in B♭
- Contra-alto Clarinet in E♭(option)
- Soprano Saxophone in B♭
- 1st Alto Saxophone in E♭
- 2nd Alto Saxophone in E♭
- Tenor Saxophone in B♭
- Baritone Saxophone in E♭
- 1st & 2nd Horns in F
- 3rd & 4th Horns in F
- 1st Trumpet in B♭
- 2nd & 3rd Trumpets in B♭
- 1st & 2nd Trombones
- 3rd Trombone & Bass Trombone
- 1st & 2nd Euphoniums
- Tuba
- String Bass
- Harp (option)
- Timpani
- Snare Drum
- Bass Drum
- Tambourine
- Crash Cymbals
- Triangle
- Tam-tam
- Tambourine
- Suspended Cymbal
- 3 Toms
- Tam-tam
- Tambourine
- Glockenspiel
- Drum Set
- Vibraphone
- Chime
- Glockenspiel
- Vibraphone
楽器編成
楽曲解説
本作品は、J.S.バッハ(1685-1750)による5 楽章からなる《無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第2番ニ短調》 BWV1004 の終曲〈シャコンヌ〉の編曲である。「シャコンヌ」とは、3 拍子の舞曲の一種であり、バロック時代にはオスティナート(何度も反復される定まった音型)に基づいた変奏曲として盛んに作曲された。バッハのこの作品でも、4 小節の定まったフレーズが32 回繰り返され、ヴァイオリン独奏でありながら257 小節に及ぶ大曲として、様々に変奏されてゆく。本編曲のタイトル《Ciaccona Allargata》は、バッハがこの楽章の冒頭に一般的に使用されている〈シャコンヌ〉ではなく、〈チャッコーナ(Ciaccona 伊)〉と記したこと、また、本編曲の方針が「拡張(アラルガータ)allargata(伊)」であることによる。ではどのような意味で「拡張」であるのか。それは大別して以下のような点である。
1.調の拡張
原曲において保たれるニ調(ニ短調、或いはニ長調)は、曲の前半においては変奏毎に移調され、ニ短調―ト短調―ハ短調―ヘ短調―変ロ短調―変ホ短調―変イ短調と、初期段階で♭が1つ付くニ短調から、7つの♭が付いた調に至る。こういった調の推移は、バッハの時代の作品群には全く例を見ないが、調的拡大は、音楽(変奏の)性格拡張やオーケストレーションの拡張にも寄与することとなった。しかしその一方で、主調であるニ短調、及び中間部でのニ長調は、構成上の核として揺るぎないものとなっている。
2.時間の拡張
一般的に、メトロノームがカウントする拍に全く正確に合わせたような演奏はあり得ないだろう。言うまでもなく、拍の延び縮みは音楽表現の重要な要素の一つであるからだ。また、旋律が装飾的に変奏された結果、1拍の長さが部分的に引き延ばされる瞬間もあろう。そういった演奏表現としての、また、音楽構造としての拍の伸び縮みは、本編曲においても形を変えて出現し、原曲における一貫した3拍子は時折部分的に引き伸ばされ、様々な変拍子へと変化する。
3.主題の拡張
BACH 主題(B=シ♭・A=ラ・C=ド・H=シ♮の音列)は、バッハの死によって未完に終わった《フーガの技法》の最終部分に使われたとされているが、彼の死後、多くの作曲家がバッハへの敬意の表明としてこの主題を自作に採用している。その例はシューマン、リスト、レーガーを始め、オネゲル、ヴェーベルンなど、枚挙に暇がない。本編曲においては、中間部の以降、原曲のオスティナート主題と(移高されたものを含めた)BACH 主題が並行し、全体を統合してゆく。
バッハの〈シャコンヌ〉がこれまでに、J.ラフ(1822-1882)による管弦楽版及びピアノ版、J.ブラームス(1833-1897)による左手のためのピアノ版、F.ブゾーニ(1866-1924)によるピアノ版、L.ストコフスキー(1882-1977)による管弦楽版など、独奏から大管弦楽まで数多く編曲されてきたことは、この曲がいかに作曲家達の創作意欲を刺激するかを物語っているであろう。そうした様々な編曲を経て、私は現在考えられる吹奏楽編曲を提示したが、その発案に関しては、当然ながら数々の編曲作品群に依拠している部分も多い。その意味では、バッハの原曲――そもそもはバッハ以前のヴァイオリン作品群の影響下にある〈シャコンヌ〉――を編曲した上述の作曲家達の作品群、そしてその再編曲としての本編曲、というように、音楽作品における歴史的「糸」の最先端として、この編曲の存在可能性を見ている。
これまで、バッハに関連する作品を吹奏楽のために編曲してきた。バッハのオルガン作品《前奏曲とフーガ「聖アン」》の前奏曲 、F.リストのピアノ、オルガン作品《バッハの名による幻想曲とフーガ》、M.レーガーのオルガン作品《B-A-C-H の主題による幻想曲とフーガ》、これら、約20年間に及ぶバッハ作品の吹奏楽編曲の集大成として、この《チャッコーナ・アラルガータ》が位置づけられると言っても過言ではない。
鶴岡東高等学校吹奏楽部、愛媛県立松山東高等学校吹奏楽部、北海道教育大学スーパーウィンズ、埼玉県立岩槻高等学校吹奏楽部、伊勢 敏之(大阪芸術大学教授)委嘱作品。
