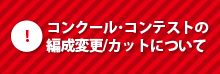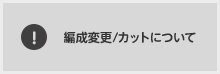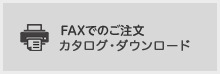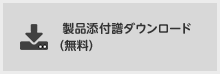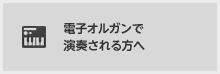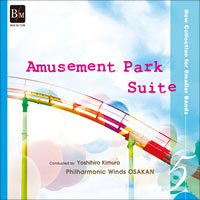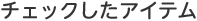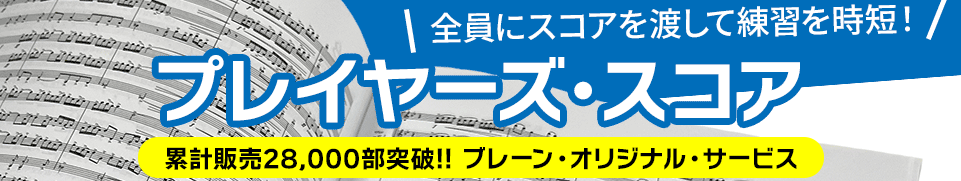
宅配スコア閲覧
楽曲詳細情報
- 作曲
- ベラ・バルトーク(Bela Bartok)
- 編曲
- 黒川圭一(Keiichi Kurokawa)
- 演奏時間
- 9分00秒 (約)
Ⅰ.バラード(主題と変奏) Ballade [3:15]
Ⅱ.古い舞踏の旋律 Old Dance Tunes [5:50] - グレード
- 3.5
- 調性
- 原調
- 主なソロパート
- Ob.(or A.Sax. Cl.) / Bsn.(or T.Sax.) / B♭Cl. / Bass Cl.(or Euph.) / A.Sax.
- Trp.最高音
- 1st:F 2nd:D
- 最少演奏人数
- 25名
- 編成
- 吹奏楽(小編成)
楽器編成
- Flute 1
- Flute 2 (doub. Piccolo)
- Oboe (opt.)
- Bassoon (opt.)
- B♭Clarinet 1 , 2 & 3
- (all 2players~)
- Bass Clarinet
- Alto Saxophone
- Tenor Saxophone
- Baritone Saxophone
- Trumpet 1 & 2
- Horn 1 & 2
- Trombone 1 & 2
- Euphonium
- Tuba (2 players~)
- String Bass (opt.)
- Percussion ※4 players~
- Timpani
- Snare Drum
- Bass Drum
- Crash Cymbals
- Suspended Cymbal
- Triangle
- Tambourine
- Glockenspiel
- Vibraphone
- Marimba
楽曲解説
ベーラ・バルトーク(1881-1945)は、ハンガリーを代表する作曲家であり、また、ピアニスト、民族音楽学者。父ベーラはピアノ、チェロを演奏し、母ヴォイト・パウラもピアノ教師という音楽一家に生まれ、幼い時から母よりピアノを学んでいた。しかし、7歳のときに父が死去してからは、国内の地方都市を転々とすることとなった。当時のハンガリーの地方都市で接することができたのは、ジプシー音楽と民謡が主で、欧州楽壇の中心にあった近代的な音楽と接する機会には恵まれなかった。
転機となったのは、1894年ポジョニ(現・ブラチスラヴァ市/スロベニア共和国)に定住することになり、当地のギムナジウムに入学してからのことである。そこで作曲やピアノを学び、本格的に音楽家を目指すこととなる。1899年ブタペスト王立音楽院に入学後、ピアニストとして頭角を現すと共に、リヒャルト・シュトラウスの「ツァラトゥストラはかく語りき」(1902年ブタペストで初演)に接し作曲意欲を大いに高められた。
一方、当時のハンガリーは独立運動が高まりつつある時期で、音楽界も古くから伝承された民族音楽が注目されるようになり、バルトーク自身も大きな影響を受けた。そのような折、作曲家であり民族音楽の研究者でもあったゾルタン・コダーイ(1882-1967)と共に伝統的な民族音楽の収集に没頭していくこととなる。バルトークは、作曲活動の一方で、現在のハンガリー、ルーマニア、スロベニアなどや、遠くは北アフリカまで広範囲に亘って民族音楽の採集にあたり、体系的な研究として現在においても重要な著作を数多く残している。
この「ハンガリー農民の歌」(Sz79/BB71)は、まず、ピアノ曲として「15のハンガリー農民の歌」が1914年と18年の2つの時期に作曲された。さらに、このなかから、第6曲〈バラード(主題と変奏)〉と第7~15曲〈古い舞踏の旋律〉の第13曲を除く各曲を作者自身がオーケストレーションした管弦楽版「ハンガリー農民の歌」(Sz100/BB107)が1933年に発表されている。
この吹奏楽編曲版は、千葉県のいすみ市立大原中学校の委嘱により編曲。2011年7月27日、第53回千葉県吹奏楽コンクール(於:千葉県文化会館)において、荘司康一指揮/同校吹奏楽部によって初演された。
編集および演奏について『今回収録のスコアは、管弦楽版と同じ〈バラード(主題と変奏)〉と〈古い舞踏の旋律〉との2つの楽章を、小編成吹奏楽用に編曲したものである。このトランスクリプションは、ピアノ版、管弦楽版どちらか一方に基づいているものではなく、双方の要素が吹奏楽に適した形で用いられている。また、原曲には含まれない打楽器なども多く追加されている。
第1楽章〈バラード(主題と変奏)〉は、ハンガリー東部のベーケシュ県にておいて1918年に採譜されたバラードの主題を変奏曲としている。この民謡は「アンゴリ・ボルバーラ」とも呼ばれ、封建時代における若い恋人達の悲劇が歌われている。冒頭、アンダンテ、7/8拍子で、管楽器のユニゾンで提示される主題が、歌詞内容の進行に対応して、徐々に様々な和声を付けされ、また変奏されて発展していき、最後はフルートの装飾句を伴って主題が強奏されクライマックスを迎える。
第2楽章〈古い舞踏の旋律〉は、比較的速いテンポの民謡9つが並べられており、いずれも1907~1912年にかけて採集されたものである。ハンガリーの代表的な舞曲のジャンルである「豚飼いの踊り」のリズムが聴かれるなど、同時期に採集された民謡に基づく「子供のために」「ルーマニア民族舞曲」「ソナチネ」などバルトークの作品群との類似性も感じられよう。もとはバグパイプによって演奏されていた最終曲では、急速なテンポで、バルトーク的な民俗音楽的な高揚感の頂点に達する。
演奏にあたって、この曲では、同じ旋律が複数回繰り返されるが、その際のダイナミクス、オーケストレーション、和声などの差異などを十分に表現できると良いだろう。一方、バルトークが魅せられた民謡そのもの味わいも十分に表出したい。フレーズの重心や頂点を意識するとともに、適切なアゴーギクによって、旋律の魅力をより際立たせることができよう。また、音色のパレットが限られる小編成吹奏楽においては、打楽器が演奏全体の色彩感に及ぼす働きは小さくない。バランスに配慮しつつ、要所ではしっかり存在感を主張することによって、演奏を一層華やげることができるだろう。』
なお、オーボエとバスーンについては、それぞれクラリネットやサックス群に代替を書き加えているので、オーボエ、バスーン奏者がいないバンドにも演奏が可能なように配慮されている。